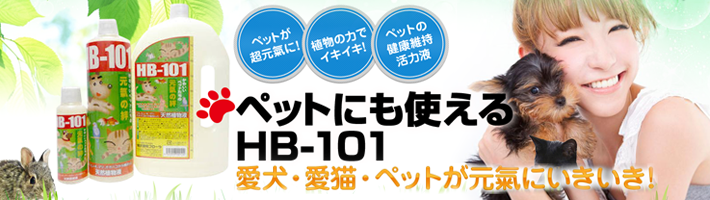猫の尿毒症はどんな症状?|原因・治療・予防まで徹底解説
2025.01.21
「猫の尿毒症ってどんな症状?」
「猫が尿毒症になる原因は何?」
「猫が尿毒症になったらどんな治療をするの?」
飼い主さんのこのような疑問を解消するために、猫の尿毒症について解説していきます。
尿毒症に繋がる腎臓機能の低下の原因やお家でできる予防法まで盛りだくさん!
ぜひ最後までご覧ください。
猫の尿毒症ってどんな病気?原因は?

猫の腎臓の機能が低下すると、本来はオシッコで排出されるはずの成分が体内に回ってしまいます。
尿素などの有害成分が血中に入り体内に溜まることで猫に様々な症状が現れる状態を尿毒症といいます。
猫の尿毒症は早急に治療をしないと死に至ってしまう、猫にとって危険な病気です。
尿毒症の原因は?
尿毒症の原因は腎臓の機能障害です。
腎臓の機能障害を引き起こすのは以下のような原因があります。
● 腎不全
● ウイルスや免疫疾患による腎炎
● 尿路結石症
● 尿路閉塞
● 外傷や生活習慣による腎機能の低下
● 水分摂取量の極度な不足
このように猫の腎臓の機能はさまざまな原因で低下することがあります。
機能低下が進んで腎臓がほとんど機能しなくなると尿毒症に繋がります。
猫の尿毒症の症状
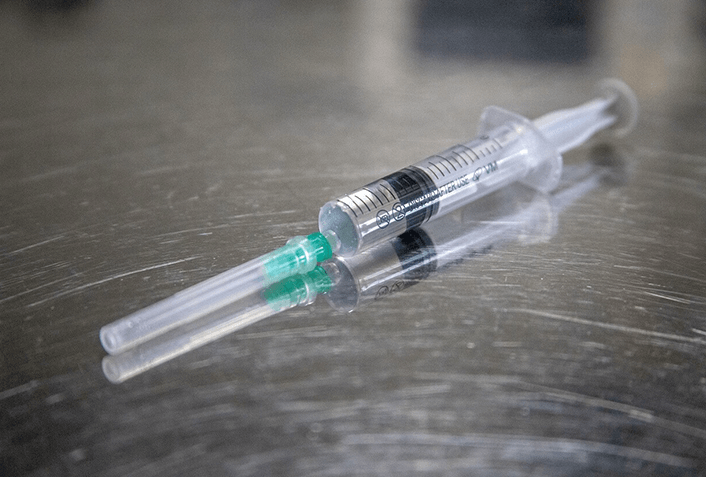
猫の尿毒症はさまざまな原因で発症することがあり、とても怖い病気です。
そんな尿毒症にはなるべく早く気がついて治療してあげたいですよね。
では、猫の尿毒症はどのような症状が出るのでしょうか。
尿毒症の初期症状・治療
猫の腎臓は75%以上の機能が低下するまで、正常に機能してくれます。
そのため猫の尿毒症や腎臓トラブルは初期症状がない場合がほとんどです。
症状が現れる場合は、食欲不振や多飲多尿・嘔吐などが見られます。
しかし、動物病院で血液検査や尿検査を行うことで異常を発見することができます。
尿毒症はなるべく早い治療が生死を分ける病気なので、定期的に健康診断を受けることが大切です。
初期の尿毒症の治療は以下のようなものが一般的です。
● 低タンパク・低リンの療法食へ切り替える
● 腎臓の負担を軽減する薬(ACE阻害薬など)の投与
● 点滴や皮下輸液による水分補給
尿毒症の末期症状・治療
尿毒症の末期は腎臓がほとんど機能しなくなった状態です。
症状が全身に現れ、深刻化していきます。
末期には以下のような症状が見られます。
● 食欲喪失
● 脱水症状
● 痙攣
● 下痢や嘔吐
● 筋力の低下・元気喪失
● アンモニア臭の口臭
猫の尿毒症の末期状態における治療は以下の方法が一般的です。
● 静脈点滴による老廃物の希釈・排出促進
● 血液透析(設備が限られており高額)
● 鎮痛・対処療法
尿毒症の末期では治療よりも緩和ケアがメインとなることが多いです。
根治を目指す治療よりも、延命や猫の苦痛緩和を目的とした処置がなされます。
猫の健康維持のためにできること

猫は腎臓の疾患が多い傾向にあり、猫の飼い主さんたちが心配する点でもあります。
また、犬とは違い普段から自由気ままで初期症状に気がつきにくいだけではなく、猫は体調不良や痛みを周りに見せないように隠す性質があります。
そのため猫の病気は発見が遅れてしまいがちで、尿毒症のような病気の場合は生死を分けることになってしまいます。
そのような事態を避けるために普段からできる健康維持対策を紹介します。
● 7歳を過ぎたら定期的に健康診断を受ける
● 普段からの健康チェック(食欲・排泄物の量・睡眠時間・生活サイクル)
● ブラッシングで皮膚・被毛の手入れをする
● 口内ケアをする
● サプリメントなどの商品を用いた栄養バランス対策を行う
今回は毎日のご飯と一緒にできる、猫の健康サポート商品を紹介します。
手作り食や複数のサプリメントを使い分けるよりも手軽に続けられるので、普段からできるサポートとしてオススメです。
その商品が「HBー101」
100%植物エキスで作られており、ペットの元気が無くなった時や、毛並みが気になるようになった時にオススメの商品です。
HBー101の愛用者には、腎臓にトラブルが生じた猫ちゃんの飼い主も多いのが注目ポイントです。
水も飲まなくなった腎臓病の猫ちゃんがHBー101を使ってから、水を飲んでくれるようになり最終的にはウェットフードも食べるようになったという口コミもあります。
まとめ

今回は、猫の尿毒症とその症状・治療法を紹介しました。
猫は腎臓が弱いと言われており、その中でも尿毒症は死に至るケースも多い危険な病気です。
初期症状が出ない場合が多いというのが怖いポイントで、気がついて時には末期で緩和ケアしかできない、という事態になりかねません。
そのような事態を避けるために、定期的な血液検査・尿検査を受けておくことがオススメです。
検査だけではなく、猫の日々の過ごし方や食欲・飲水量などをよく観察し把握しておくことがとても大切です。
大切な愛猫が可能な限り健康で長生きできるように、健康なうちから対策と予防をしていきましょう。